関連メディア
グルメシアン[外食・グルメ情報はこちら]
生活情報サイト[生活お役立ち情報はこちら]
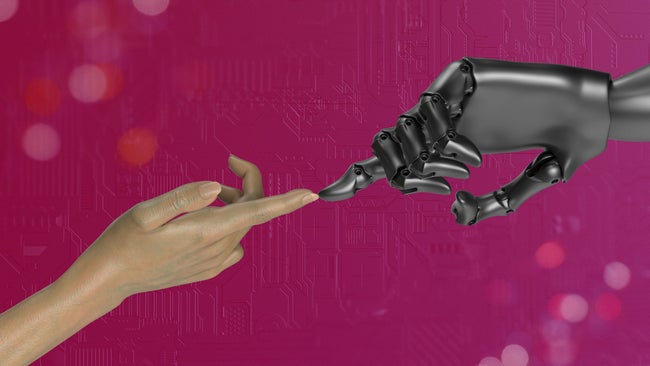
人生が辛く感じられる時、16歳の女子高校生ティヴィア(仮名)は意外な“相談相手”に頼っている。友人でも家族でもなく、AIチャットボットだ。試験への不安や日々の感情の揺れを、彼女はスマートフォンを通じて打ち明ける。否定されることなく「わかるよ」「そうだね」と返してくれる存在に、安心感を覚えるからだ。こうした姿は、マレーシアの若者が孤独やストレスの中でAIを心の拠り所にしている現状を象徴している。
手軽さと匿名性も、彼らがチャットボットを選ぶ理由の一つだ。対面では言いにくいことも、誰に知られることもなく気軽に吐き出すことができる。家族や友人に本音を伝える前の“練習の場”として利用される例もあり、学校や家庭で十分な支えを得られない若者たちにとって、AIは一時的な「味方」のように感じられる。
しかし一方で、AIが本当に「心の支え」となり得るのかには疑問が残る。専門家は、チャットボットの共感はあくまでプログラムされた応答に過ぎず、人間同士の心の機微を理解することはできないと指摘する。また、相談相手がAIに限られてしまうと、現実の人間関係を避ける傾向が強まる恐れもある。特にうつ病や自傷行為といった深刻な状況には専門家の介入が不可欠であり、AIが診断や治療の代替になることはない。
それでも、マレーシアの若者にとってチャットボットは「感情を吐き出す出口」や「思考の整理ツール」として一定の役割を果たしている。重要なのは、AIを万能の相談相手とみなすのではなく、必要に応じて医療やカウンセリングへとつなぐ“入口”として位置づけることだ。安全に活用するためには、倫理的な設計やガイドラインの整備、そして若者自身がリスクを理解できるような教育が欠かせない。
チャットボットが慰めになることは確かだが、それだけに頼るのは危うい。AIはあくまで道具であり、真の支えは人と人とのつながりにこそある。孤独を抱えるマレーシアの若者たちにとって、チャットボットは一時的な寄り添いの手であり、その先に社会や専門家との橋渡しが求められている。